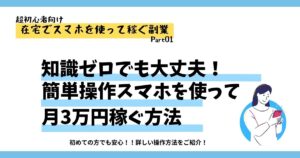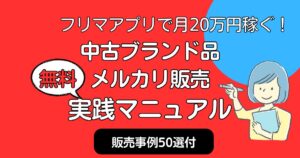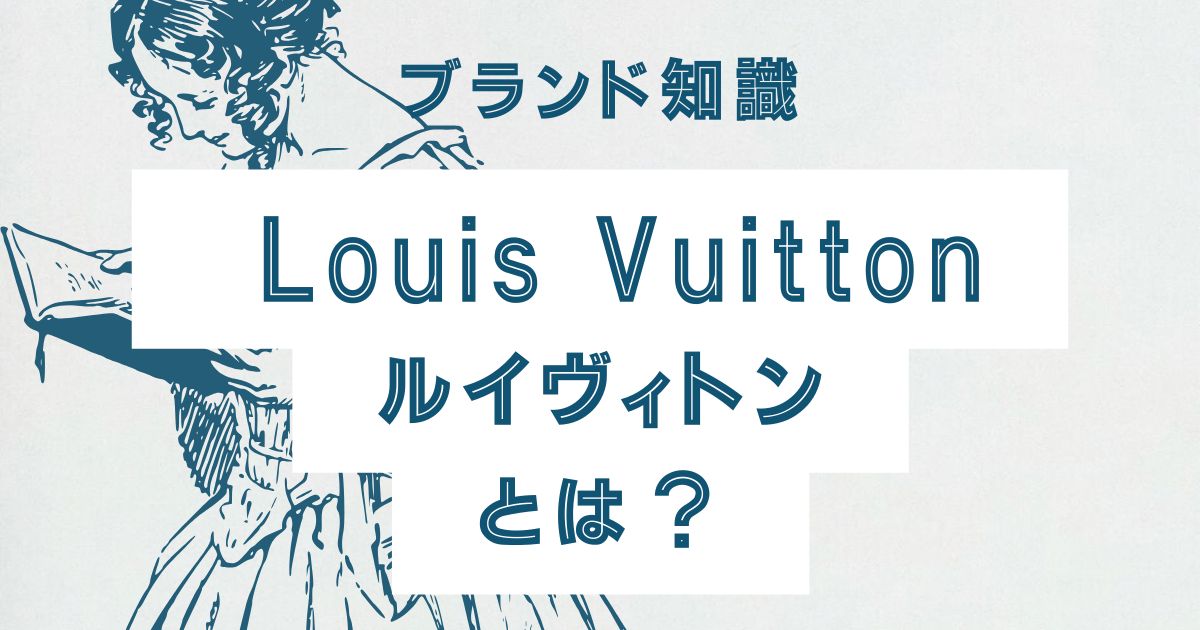中古ブランド品やアンティーク雑貨などを安く仕入れて販売する「物販ビジネス」に興味はあるけれど、どこで仕入れればよいのか分からない――そんな方にぜひ知ってほしいのが「古物市場(こぶついちば)」の存在です。
古物市場は、プロのバイヤーや業者が集まる中古品のオークション会場で、思わぬ掘り出し物をお得に手に入れることができるのが魅力。
しかし、初めての方にとっては「参加方法が分からない」「リスクはないの?」といった不安もあるはず。
この記事では、初心者の方向けに古物市場の基本的な仕組みから、仕入れの流れ、参加するメリット・デメリットまで、わかりやすく丁寧に解説していきます。副業や転売を始めたい方は必見です!

古物市場を使った物販は特別なスキルや知識がない方でも始めやすい副業の一つです。
今回のブログでは、初心者向けに市場の仕組みやメリットとデメリットなどについて説明します。
本記事のテーマ
【初心者必見】古物市場とは?仕入れの基本・メリット・デメリットをわかりやすく解説!
- ①古物市場とは?
- ②古物市場に参加するには?
- ③古物市場のメリット
- ④古物市場のデメリット
- ⑤古物市場に参加する時のマーナ
- ⑥まとめ
①古物市場とは?

古物市場は主に中古の商品をオークション形式で買うことができるところです。もちろん、新中古品も出品されますが、多く出品されるものは中古品です。
古物市場の種類は下記のものがあります。
ブランド市場:ルイヴィトンやシャネルなど名の高いブランド品を扱います。 バッグ、財布、アクセサリー、スカーフなど様々なブランド品が出品されます。
道具市場:洗濯機や冷蔵庫、家具、ゲームソフトなど様々な生活用品やフィギュアや骨董品など趣味関係の商品が出品されます。
ネットオークション:こちらはブランドオークションや道具オークションがありまして、インターネットで開催されます。
②古物市場に参加するには?

古物市場に参加するには、かならず古物許可証が必要になります。 古物許可証の取得方法は下記のページにてご確認ください。取得の代行を行っている業者さんもいますが、取得方法はそれほど難しくないので少しでも節約する意味で自らやった方が良いと思います。下記のサイトで分からないことがあれば、管轄の警察署に問い合わせると優しく教えてくれます。
古物許可証を取得しても、古物市場によってはそれぞれ参加条件を設けているところもあります。
例えば、
➡古物の取り扱いの業務歴を問われる
➡すでにその市場の会員になっている方の紹介がないと入会できない
などです。
それから、入会金や年間費、参加費、落札手数料などは市場によって異なるので事前に市場に問い合わせしましょう!
③古物市場のメリット

古物市場には下記のようなメリットがあります。
- 仕入れが安定的
- 商品をお安く買うことができる
- 仕入れて、自家用にしたり販売することができる
- 仕入れた商品を市場に戻すことができる
- 情報交換ができる
それでは、メリットを詳しく説明します。
①仕入れが安定的
会場で開かれる多くの市場は午前10時~午後18時ぐらいまで開催されます。一度に数万点の商品が取引されるので、仕入れがとても安定しています。しかも、日本では古物市場がたくさんあるので、様々な市場で色々な商品を仕入れることができます。
因みに、私は現在毎月約6カ所の市場に参加しています。ある市場は月1回、ある市場は月3回、ある市場は週4回開催されるので、販売する商品が足りなくなる心配はありません。
②商品をお安く買うことができる
市場では日本で中古品を販売しているリサイクルショップやブランドショップより商品を安く買うことができます。これらのショップはお客さまより直接買い取りをしたり、古物市場で仕入れた商品を店頭で販売しています。それから、古物市場に商品を出品したりもしています。
③仕入れて、自家用にしたり販売することができる
私の知合いは自分用の商品を買うため古物市場に参加しています。彼は、ロレックスやルイヴィトン、グッチといったハイブランド品はショップより市場が断然お安いことを知っているので、販売目的ではなく自家用の商品を仕入れるため市場に参加しています。古物許可証を取得して、市場の参加条件をクリアすれば誰でも市場に参加できるので、自分へのご褒美のみならず家族や知人へのプレゼント探しにも古物市場を利用できます。
因みに、私も市場で競ったシャネルのバッグを二つ、バーバリーの財布を一つ、ブランド品のアクセサリーを何点か自分用に使っています。それから、市場で競ったたくさんの商品を日本ではメルカリや楽天、海外ではebayにて販売しています。これらのプラットフォームにて販売している商品は100%古物市場にて仕入れた商品ですので、みさなんも古物市場がどんなに優れた仕入れ先なのかは簡単に想像できると思います。
④仕入れた商品を市場に戻すことができる
これはかなり嬉しいシステムの一つです。詳しく説明すると、市場で買った商品で販売できなかったり、商品が汚かったり破れたりして販売用にできない場合、その商品を市場に出品して販売することができます。
私は販売できなかったり、山で仕入れて自分が販売したくない商品を月1回市場に出品して売上を作っています。最初この手法に出会った時は、かなり便利なシステムだと思いました。おかげで、売れ残りの心配などはありません。
⑤情報交換ができる
市場では市場歴が長い方が多く参加していまして、先輩達にアドバイスをしてもらったり、販売や仕入れ先などの情報を教えてもらうことができる魅力があります。
私が最初市場に参加した時は右も左も分からないことだらけでしたが、他の参加者の方が、商品の買い方や、仕入れ値、販売値、他の市場の情報をなどを教えてくださいました。そのおかげで、市場に早く慣れることができ、利益を出すこともできたので、市場は本当に一石二鳥の場所だと思いました。
④古物市場のデメリット

- 声を出して商品を競らないといけない:魚や美術品のせり風景
- 相場勘がないと商品を高く買ってしまう:プロが多いので買いたい商品の相場を知る必要がある
- あせらず、色々な市場に参加して他の人達がなにをどのぐらいの値段で競っているか観察する必要がある
- 専門用語が分からないと本当に買いたいものが買えなくなる場合もある
これから説明するデメリットの部分は古物市場初心者やまだ市場歴が浅い方向けです。私が初めて市場に参加して数か月かなり難しかったことをデメリットとしてお書きしますので、これから古物市場の物販を目指している方は参考にして頂ければと思います。
①市場で商品を競る時、オークショナーが聞こえる声で金額を言わなくてはいけません。声が小さかったり、はっきりとした金額を言えない場合うまく商品を競ることができません。 魚や美術品の競り風景を思い出すと参考になると思います。
オークションに慣れない内には声に出すことがなかなか難しく、その結果商品が買えなかったりします。 私も最初これがかなり難しいと思いまして、暇がある時は金額を声に出す練習をたくさんしました。それから、商品を競る時は瞬発力も必要になります。例えば、他の参加者が自分の言った金額を上回るとすぐその金額を超えた指値を言う必要があります。簡単に聞こえるかもしれませんが、実際オークションに参加してみると、声に出すこととすぐ上回る金額で競ることがとても難しいと体験できると思います。
②相場勘がないと商品を高く買ってしまう:プロが多いので買いたい商品の相場を知る必要がある
市場ではその場で商品を競るため、ある程度の相場勘がないと利益が出ない金額で商品を買ってしまう場合があります。私は何回も売値とほぼ同じ値段で商品を買ってしまい、損したことがあります。その時を振り返ると、市場に慣れていなかったことと平均的な売値を全然調べないで競ったのが悪かったと思います。
古物市場に慣れない内は、なるべく後ろの席に座り、買いたい商品を見つけたらすぐスマホで検察するのをおすすめします。なぜ、後ろの席に座るかというと、商品がオークショナーに届くまで時間を稼ぐことができるので、その間スマホで画像検索やメルカリなどで商品名で現在の販売値や実際商品が売られた金額を調べることができるからです。後ろの席は、競りにかかっている商品がよく見えない短所もありますが、相場も調べず利益が出ない商品を仕入れるよりはマシだと思います。それから、真中の席は商品が見えない時立ち上がって競ることができませんので、市場に慣れていない時は一番後ろか角の席を選ぶことをおススメします。
③あせってしまい商品を高く競ってしまう場合がある。
市場初心者は、何回も競りがうまくいかないとあせてしまい、相場より高く競り上がって結果利益が薄いか利益が出ない金額で商品を買ってしまう場合が多くあります。私も最初は、販売値も知らず競り上がった結果利益が取れなかった場合が多くありました。その時の失敗で分かったことは、
➡あせってはいけない
➡市場の先輩達が何をどのぐらいの価格で競るかを観察&メモする
この二つがとても重要だと思いました。
現在は、今までのメモや実際販売してみて妥当な仕入れ値を元に競りをしているので、前よりは利益が取れやすい商品を見つけることができました。
④専門用語が分からないと本当に買いたいものが買えなくなる場合もある
市場では、金額を言う時専門用語を使っている方もいます。
例えば、パゴ、ドン、ヒャッカン、センマイなどという人がいます。この用語は符丁(フチョウ)と言います。市場でよく使う符丁には下記のようなものがあります。
パゴは8,500、85,000
ドンは10,000、100,000
ヒャッカンは 3,500 35,000
センマイ 1,250 12,500
このような用語が分からないと、競り上がることができない場合があります。
オークショナーによっては、この専門用語を皆が分かる数字で直してくれる場合もありますが、大概は専門用語のままで競りが進みます。私はこの用語がかからず何度か下回った金額を言ったことがありました。オークションでは、相手より上回る数字を言わなくてはならないのでこのような符丁を覚えておくとよいでしょう!
⑤古物市場に参加する時のマナー

古物市場には全体的なルールがあります。例えば、席や撮影、あとのり、ちょいのりなどのルールがあります。こちらでは市場に参加する際に知っておくと便利なマナーについて説明します。
①席:市場によっては椅子が置いてないところもありますが、椅子があっても全席を指定席にしているところもあったり、前の一列目が指定ではないですが、決まった方が座るところもありますので、市場に慣れていない時はなるべく後ろに座るか主催者に聞いてから席につくのが良いと思います。
私は最初何にも知らずに、前に座りましたが、主催者より「この席にいつも座る方がいるので違う席に移動してください」と言われびっくりしました。席に名前が書いてるわけではありませんが、ある程度の席が決まっていることを初めて知りました。
②撮影NG:商品が流れている間、画像検索をするための撮影は大丈夫ですが、市場の競り風景を撮影したり録音することは禁じられています。Youtubeで古物市場を検察すると競り風景が見られる動画がありますが、それはほとんど主催者が取っているか主催者の許可を得て撮影されたものですので、勝手に撮影すると後で問題になる場合があります。
③聞き取れやすい大きな声で指値を入れること:当然ですが、声が小さいとオークショナーまで声が届きませんので大きな声で競ることが大切です。私は最初声に出すことがとても恥ずかしかったのですが、今はすっかり市場に慣れて声も大きくなりました。
④オークショナーより下回る値を指すのはNG:市場ではオークショナーが3000円と言ったら、3000円と言うか、3000円を上回る金額を言わないといけません。もちろん市場に慣れている方も間違って下回る金額を言う人もいますが、基本的はこの行為はNGとされています。
⑤遅れて声を出すのはNG(他の参加者の希望入札金額を聞いてから、遅れてそれを上回る金額を言うのはNG)これは後のりといいます。私が最初に市場に参加した時、何回も後ノリをして参加者の方に注意されたことがありました。 その方いわく、後ノリは市場では禁止されているのでこのまま後ノリを続けると市場の皆さんに嫌われるとのことでした。市場初心者ですと、やりがちなミスですが、もし数字を言うのが難しかったら下記をおススメします。
オークショナーが5000円と言ったら、とりあえず、「はい」と答えて、違う人が5500円と言ったらすぐ6000円と言います。こうすると、相場観があんまりない方もオークションについていけます。
⑥前の人の入札金額に少しだけ上乗せして入札をするのを「ちょいのり」といいます。参加者はなるべく安く商品を買いたいので、ちょいのりをしがちですが、これは市場によって嫌われるところもありますので参加した市場の様子を観察する必要があります。
⑦間違って指値を出して落札した時は速やかにオークショニアや事務局の方に伝えることが大切です。市場では中古品がたくさん出品されるのでそれぞれの状態を細かくチェックすることが難しいです。なので、他の参加者より自分が競った商品について、「あれジッパー壊れてるよ」、「ハンドルが修理されてる」などと言う場合がありました。それから、本物だと思って落札したバッグが偽物だったりする場合もありました。この場合はすぐオークショナーや主催者に伝えるとオークションをやり直したり、偽物を取り下げしてくれます。
まとめ
以上が、古物市場の仕組みやメリット、デメリットに関する内容です。皆さんの目標は、毎月少しでも稼げる副業探しだと思いますので、上記の内容を参考にし市場で仕入れて国内や国外で販売してみてください!
私は市場で仕入れたものをメルカリやEbayなどのプラットフォームで販売する方法は、特別なスキルや知識が必要ではないので誰でも始めやすいと思います。もちろん、それぞれのプラットフォームを使う時注意する事項や効率的な販売手法などはありますが、古物市場は副業のみならず自家用の商品を仕入れる楽しみを味わえる場所でもあります。
この副業は誰でも始めやすいのでその分競合もたくさんいるので、相場観や売れ筋商品について研究する必要があります。それから、市場のルールやマナーを知っておくとより良い仕入れができるようになります。
この記事が皆さんに少しでもお役に立つことを祈りながら今回の記事を終えたいと思います。